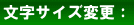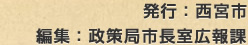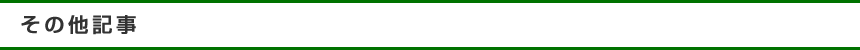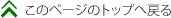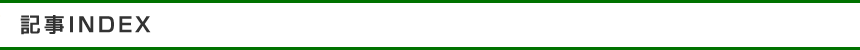多文化共生を考える
『人権文化の花咲くまち 西宮』を目指して多様な視点から学ぼう!
「ステレオタイプ」に気をつけて~「わたし」と「あなた」の交流を!
日本語教育支援グループ「ことのは」
理事長 矢谷久美子さん
地域日本語教室では、さまざまな背景の参加者が日々活動しています。なぜ、今、その地域に暮らしているのか、理由はそれぞれです。世界中からやってくる教室参加者から聞く話は、本やメディアで得た情報よりはるかに興味深く、学びが多いものです。私は食いしん坊なので、食べ物の話でいつも盛り上がります。
私は生まれも育ちも大阪で、日本語教師になって海外で仕事をするまで、地元を離れたことがありませんでした。狭い世界で暮らしていたわけですが、教師になりたての頃は、異文化を持つ学習者に対しての接し方を間違えていたことがあります。特定の国の人をひとくくりに捉えて固定観念を抱いて判断していたのです。たとえば、ブラジル人はサンバが好き、韓国人はキムチ!という思い込みです。私が出会ったブラジル出身の技術研修生はサンバには興味がなく、趣味は盆栽でした。また、キムチが苦手な韓国の人もいました。私は学習者とのやり取りで、自分の勝手な思い込みで発言したり、行動したりしていたことに気付かされ、何度も反省しました。
日本語の練習で、「あなたの国では?」と問いかけることがありますが、大国から来た人は意見の違いから、よく口論になります。大きな国ですから、地域によってさまざま違いがあるのは当然です。「あなたは?」と聞けば良かったですね。
日本語教室の活動は、日本人と外国人の交流ではありません。今、この地域に住んでいる「わたし」と「あなた」の交流です。考えてみれば、国が同じでも、世代や環境等で人の考えはさまざまです。外国人参加者に「日本料理といえば?」と聞くと、「すし、てんぷら、すき焼き、しゃぶしゃぶ」と答えます。最近ではラーメンが人気です。でも、私たちの普段の食生活を考えたとき、日常的にそれらの料理を食べているかというと、はなはだ疑問です。私の場合、新米の時期は、おにぎりとみそ汁、それに焼き魚があると完璧。名前も無いような煮物、炒め物を食べているように思います。
もし、近くに住んでいる外国の人と交流する機会があれば、家庭料理の話をしてみてください。おいしい家庭の味に出会えるかもしれませんよ。
【問合せ】秘書課(0798・35・3459)