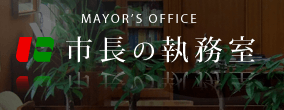令和7年度西宮市施政方針
更新日:2025年2月20日
ページ番号:59469022

令和7年度西宮市施政方針演説(令和7年2月18日)
目次
令和7年度西宮市施政方針
本日ここに、西宮市議会第10回定例会の開会に当たり、新年度予算案をはじめ諸議案の提案とともに、私の施政方針を申し上げ、議員各位並びに市民の皆様のご理解とご支援を賜りたいと存じます。
はじめに
今年は阪神・淡路大震災の発生から30年という節目の年になりました。改めて震災の教訓を胸に刻み、地域の皆様とともに災害に強いまちを作っていく、そうした決意を新たにするものです。
そして4月にはいよいよ、市制施行100周年という、本市にとって大変大きな節目を迎えます。明治維新以降の近代化が急速に進み、酒造業や鉄道も大きく発展する中、本市は1925年(大正14年)に市制をスタートしました。それまでに市制へと移行していたのは、県都や城下町、商都ばかりでしたが、そうではない、民が主体的な存在という特徴を持つ西宮市が市制へと移行したことは、本市が地方自治における新たな時代のさきがけとして位置づけられる、と言えるのではないでしょうか。
市制施行以来、大正から令和まで4つの時代を歩み、今、節目の年を迎えるわけですが、今年は記念式典を皮切りに、まちなかでも「西宮市制100周年記念」の冠がついた様々なイベントや事業が実施されることとなります。これらの事業をしっかりと支援し、積極的な情報発信を行うことで、市民の皆様とともに記念すべき年をお祝いできるよう、より一層の機運醸成を図ってまいります。
<市の将来像について>
本市の目指すべき姿は、文教住宅都市宣言の一節にある「憩いと安住の地」であり、この目指す姿を市民の皆様と共有し、維持し高めていくことが私の使命であると考えています。
そのためにも、市民生活を支えるソフト事業は今の水準を維持しながら、状況に応じて、適切な見直しによって持続可能性を高めるとともに、良好な住環境の保全と向上、公共施設やインフラ整備など、ハードへの投資も厳選しながらバランスよく行うことで、文教住宅都市としての価値を保ち、選ばれ、住み続けていただく、そしてこのまちに住むことで誇りと憩いを感じていただける、そういったまちであり続けることを目指して、全力で取り組んでまいります。
<財政構造改善の取組>
現在本市では、社会保障関係経費や人件費など行政コストの増加が、税収等による市の収入の伸びを上回る厳しい財政状況が続いており、市の最優先課題として、令和6年度より財政構造改善に取り組んでおります。
持続可能な市政運営を行うためには、一時的な財政対策だけでなく、財政構造そのものを変えていくことが必要です。先頃策定しました「西宮市財政構造改善実施計画」において、具体的な取組項目やその効果額、取組のスケジュール等をお示ししたところですが、財政収支の均衡を図り、持続可能な市政運営を実現できるよう、一つひとつの取組を着実に積み重ねてまいります。
続いて、新年度に実施する主要な事業・施策について、本市の最上位計画である「第5次西宮市総合計画」の体系に沿ってご説明いたします。
1 住環境・自然環境
基本計画の第1部「住環境・自然環境」についてです。
本市の特徴である利便性と自然が調和したまちづくりを継続し、限られた財源の中でも厳選してハード整備に取り組んでいくことで、まちとしての価値や魅力を更に高め、引き続き「住みたいまち」としての高い評価を維持していきたいと考えております。また、事業実施にあたっては、地域団体や民間事業者との協働によって、より効果的な取組となるよう進めてまいります。
市の臨海部では、令和5年度に策定した「臨海部の土地利活用構想の基本方針」に基づき、各埋立地における大規模公園の一体的な価値向上を目指しており、鳴尾浜臨海公園南地区については、パークPFI等の手法による民間活力を導入した再整備を想定し、令和7年度内に事業者を選定できるよう、公募等の作業を進めてまいります。
阪神西宮駅の北側地区では、地区計画の決定及び都市計画公園である和上公園の区域の変更とともに、土地区画整理事業の施行認可など工事着工に向けた手続等を進め、同駅北側地区が本市の都市核にふさわしい賑わいと活力のある駅前空間となるよう、引き続き民間事業者と連携して取り組んでまいります。また、同地区の公民複合施設に移転整備を予定している中央図書館につきましては、移転整備基本構想及び基本計画の具体化に向け、着実に準備を進めてまいります。
市役所本庁舎周辺地区では、居心地が良く歩きたくなるウォーカブルなまちなかづくりを進めるため、令和6年度末に完成する本庁舎前空間のリニューアル工事に続き、六湛寺公園の再整備に向けた調査設計を行います。
また、江上町の市有地については、旧江上庁舎と旧保健所庁舎の解体工事を進めるとともに、跡地活用について、公園・広場スペースの確保など地域課題の解消と財源の確保を図るため、プロポーザル方式による民間事業者の公募手続を進めてまいります。
JR西宮駅南西地区では、卸売市場の再整備後、引き続き沿道施設及び複合施設の整備を進めることで、都市核にふさわしい新たな都市機能を導入し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図り、賑わいと魅力ある都市空間の形成に取り組んでまいります。
市営住宅については、長寿命化を進めるとともに、公共施設マネジメントの観点を踏まえた戸数の適正管理を進める一方、真に住宅を必要とする住宅困窮者に効果的に供給する方策を検討します。また、既存ストックについては、本市の政策課題解決のために活用できるよう取り組んでまいります。
阪急武庫川新駅設置事業については、令和7年度から国の社会資本整備総合交付金の事業採択を受け鉄道施設等の詳細設計に着手し、令和13年度末には事業を完了したいと考えております。引き続き、地域の皆様のご意見をお聞きするとともに、尼崎市や阪急電鉄と協力して、駅開業に向けて取り組んでまいります。
コミュニティ交通については、既に本格運行している生瀬地区・名塩地区に続き、甲陽園地区において、現在試験運行が実施されております。引き続き、地域が主体となって進めるコミュニティ交通の取組に対して積極的に支援してまいります。
2 子供・教育
次に、基本計画の第2部「子供・教育」についてです。
全国的に少子化が進む中、文教住宅都市を標榜する本市にとって、子供・教育に関する施策は最も重要な政策分野であると考えております。各施策を効率的、効果的に進めるとともに、多様化・高度化する支援ニーズへの対応に向けては、福祉・教育・保健医療の各部門が連携するなど、より充実した体制で取り組んでまいります。
市制施行100周年の節目に当たり、ここから未来への一歩を踏み出す上で、私たちには、次世代を担う子供たちへより良いまちを引き継ぐ責任があると考えています。この思いを形にすべく、全ての子供たちが健やかに育つように、また安心して子育てができる環境づくりに向けて、社会全体で子供・子育てを支えていく機運を醸成し、子供たちの声を踏まえたまちづくりを進めていくための基盤となる「(仮称)宮っ子つながり支える条例」の制定に向けた取組を、着実に進めてまいります。
この条例において、社会全体で子供・子育てを支えるという理念を示すとともに、子供一人ひとりの人格を尊重するスタンスのもとで、子供自身の気持ちに寄り添い育ちを支えるための機関設置を盛り込み、市として子供の人権を守る体制を強化していくことを目指してまいります。
「西宮市幼児教育・保育のあり方」に基づく取組につきましては、令和6年11月にアクションプラン[Part3]が完成し、市内全域の公立幼稚園と公立保育所の再編計画等の策定が完了いたしました。今後は浜脇こども園の開園を起点にアクションプランを着実に推進するとともに、令和7年4月に設置する「幼児教育・保育センター」を中心に、公立、私立、幼稚園、保育所の枠を超えて連携・協力し、本市の幼児教育・保育の質の向上を図り、就学前から就学後につながる切れ目のない一貫した子供の教育・保育の実現を目指してまいります。
本市におきましては、保育ニーズは依然として増加を続けております。今後の少子化も見据えながら、既存施設の有効活用などにより、引き続き待機児童の解消に向けて取り組んでまいります。また、誰一人取り残さないための取組として、特別支援教育・保育補助事業の拡充により、支援や配慮が必要な子供たちの受入体制についても整備を進めてまいります。
児童福祉法及び母子保健法の改正を踏まえ、令和7年度より新たに「こども家庭センター」を設置し、児童福祉と母子保健の両面から、全ての妊産婦、子育て世帯、子供に対し、一体的に相談・支援を行う体制を整えます。
また、子育て世帯の負担軽減を図るため、令和7年7月より乳幼児等・こども医療費助成制度を拡充し、1歳から高校生世代までの入院に係る医療費を無償化いたします。通院に係る医療費の無償化についても、実現に向けて、財政状況の改善などに努めてまいります。
幼児期において、言語の理解能力や社会性が高まり、発達の課題が認知されやすくなる5歳の時期は、保健、医療、福祉による対応の有無がその後の成長や発達に大きく影響を及ぼします。このことから、5歳児を対象に発達の目安を示したリーフレットを送付するとともに、不安がある方に対しては、保健福祉センターにおいて、一人ひとりの特性に合わせた支援につなげるための発達相談支援を開始します。また、併せて就学後も切れ目なく適切な支援が継続できるよう、教育委員会との効果的な情報共有について検討してまいります。
留守家庭児童育成センターのニーズは、保育ニーズと同様に年々増加傾向にあり、待機児童の解消が大きな課題となっております。待機児童の発生が見込まれる施設においては、学校施設や近隣の公共施設を活用するなどの取組により、受入枠の拡大を図ってまいります。
また、放課後キッズルーム事業については、全ての児童に自由で安心できる居場所を提供できるよう、引き続き事業の拡充に努めるとともに、留守家庭児童育成センターとの連携を進めることにより、効果的な放課後施策の推進を図ってまいります。
令和7年度の新たな取組として、家庭や学校以外に居場所が必要な子供を受け入れ、個々に応じた支援を包括的に提供する児童育成支援拠点事業や、ひとり親家庭の養育費確保のための強制執行申立てに係る費用補助を開始し、支援が必要なご家庭に対する取組について、更なる充実を図ります。
本市の不登校児童生徒数は、令和3年度以降、3年連続で1,000人を超えており、小学校、中学校ともに全国平均よりも発生率が高くなっています。不登校は、様々な要因によって誰にでも起こり得るもので、これにより継続的な学びの機会が失われることは、子供の将来に非常に大きな影響を及ぼすものであることから、本市としても取組が必要です。そこで、校内サポートルームの設置など、不登校児童生徒の多様な学びの場の充実を進めてまいります。さらに、選択肢を広げるとともに、すべての子供たちが安心して学べる学校づくりのモデルとなるよう、「学びの多様化学校」の設置に向けた検討を進めてまいります。
また、そもそも子供たちにとって、学校に自分の居場所があると実感でき、学校が自身の個性や能力を十分に発揮できるような場所になることが大切であり、そのために誰一人取り残さない授業づくりや、児童生徒理解を基盤とした生徒指導などの取組を展開してまいります。
特別な支援や医療的ケアを要する子供の数は増加しており、個々の教育的ニーズも複雑化・多様化しております。これらの状況を踏まえ、引き続き早期からの一貫した適切な支援体制の構築を図り、学校における合理的配慮を行うための基礎的環境整備に取り組むとともに、多くの教職員が実践的な指導力の向上を図るための研修を実施することで、誰もが共に学べる環境づくりを進めてまいります。
学校における部活動については、国が示した中学校における部活動の段階的な地域移行の方向性を踏まえ、子供たちが将来にわたってスポーツや文化芸術に親しむことができる機会を確保する必要があります。本市では西宮での活動を楽しめるようにとの思いから「プレイにしのみや(プレみや)」と愛称をつけ、策定した基本方針に基づき活動団体の募集を行っています。令和7年度では部活動の地域移行を一部で先行実施し、登録団体を増やしながら、令和8年夏には円滑に本格実施を迎えられるよう、教育委員会と市長部局が連携し、子供から大人まで希望する誰もが参加できる、文教住宅都市にふさわしい持続可能な環境づくりを目指して取り組んでまいります。また、部活動の地域移行を進める上では、活動団体が体育館や武道場、校庭などを使用できることが不可欠であり、そうした環境が実現できるように、必要な整理を進めてまいります。
教員の負担軽減については、教育の質を確保する上でも重要であるため、定時退勤を促す取組を進めるとともに、新たに事務処理の効率化を図る服務管理システムの導入に着手するなどDXを推進し、校務改善に取り組みます。また、教育委員会からスタッフを学校に派遣し、学校だけでは解決が困難な課題の解決支援にも、継続して取り組んでまいります。
学校施設については、「西宮市学校施設長寿命化計画」に基づき、効率的かつ効果的な建替・改修を推進しながら、今後の人口減少を見据えた中長期的な視点で、学校の適正規模や適正配置について検討を行うための、基本的な考え方の整理を進めます。
これまで継続して取り組んできた学校体育館の空調整備につきましては、令和7年度に完了する見込みであり、老朽トイレの環境改善及び洋式便器化についても、引き続き取り組んでまいります。
3 福祉・健康・共生
次に、基本計画の第3部「福祉・健康・共生」についてです。
福祉、医療等に係る行政需要が増大する中で、各施策を継続・充実し、かつ効果的に進めるためには、既存の事業を見直し、時代に適合した新たな行政サービスを提供する必要があると考えます。市民一人ひとりが生き生きと自分らしい生活を営めるよう、市民の皆様が主体となった事業にもチャレンジしてまいります。
少子高齢化や家族機能の低下、地域のつながりの希薄化に起因して、地域では従来からある福祉課題に加え、ひきこもりや8050問題、ヤングケアラー等の複合化・複雑化した支援ニーズを抱えた、新たな福祉課題が発生しています。これらの課題への対応を強化するため、令和7年度から新たに「参加支援事業」などを開始し、本格的に重層的支援体制整備事業を実施するとともに、「ひきこもり地域支援センター」を設置し、様々な福祉課題の解決に取り組んでまいります。
また、今後増加していくことが予想される認知症、軽度認知障害の早期発見・早期対応を推進するため、高齢者を対象とした認知症無償診断事業について、令和8年中の実施に向けた準備を進めてまいります。
比較的軽度である「要支援」の認定を受けた方に対しましては、できないことを補う支援だけでなく、ご本人ができることや、やりたいことに着目し、自分で再びできるようになる「リエイブルメント」に重点を置く支援が重要です。また、「リエイブルメント」に着目した支援においては、その状態を本人が継続できる「セルフマネジメントスキル」の向上が必要となります。これらを踏まえ、令和7年度から「リエイブルメント」と「セルフマネジメントスキル」の向上を目指した支援を行うため、要支援認定者を対象に短期集中型サービスの導入を試行実施いたします。
「健康寿命の延伸」を目指す上で、「歯・口腔の健康」については、若い世代の歯周疾患対策に取り組むことが重要です。このことを踏まえ、現在40歳、50歳、60歳、70歳を対象に実施している歯周疾患検診について、令和8年1月から、新たに20歳、30歳を対象に加えて実施いたします。
市立中央病院と県立西宮病院の統合再編新病院「(仮称)西宮総合医療センター」につきましては、令和8年度上半期の開院に向け、建設工事も順調に進んでおり、令和7年度は医療機器の選定及び購入や、移転計画策定への着手を予定しております。
統合再編後の中央病院跡地のうち本館敷地部分については、市の財政状況を勘案し、民間医療機関との対話も踏まえて、当初計画を見直し、より有効な跡地活用が図られるよう、民間医療機関の誘致を前提として土地を一体的に売却する方針といたします。また、「高齢者福祉ゾーン」については、甲陽園本庄町市営住宅跡地を代替地として売却を進め、病院北側駐車場の敷地については、予定通り「子育て関連施設ゾーン」として活用いたします。
全ての人が互いに個人の尊厳と人権を尊重し、価値観や生き方の多様性を受容し支え合うことができる共生社会を目指し、市民一人ひとりが行動を起こすきっかけとなり、学び合い、共に楽しむことを通して、生きづらさへの気づきや寛容な文化の醸成につながるよう、人権に関する教育・啓発に努めてまいります。
平成12年(2000年)に開設した男女共同参画センターが25年の節目を迎えるため、市制施行100周年の機運を捉え、ジェンダー平等の実現を目指して記念事業に取り組みます。
また、今年で終戦・被爆から80年が経過し、戦争や被爆の経験のない世代が増え、戦争・被爆体験の風化が懸念されることから、命の大切さ、平和の尊さなど、平和意識を高める機会を継続して提供してまいります。
4 都市の魅力・産業
次に、基本計画の第4部「都市の魅力・産業」についてです。
文化・芸術やスポーツ、生涯学習などに親しむ市民の姿は、文教住宅都市の心豊かな暮らしを象徴するものです。様々な「まちの魅力ある資源」を生かし、豊かな市民生活とまちの更なる発展を実現させてまいります。
より良い地域社会を実現するために、主体的に役割を果たそうとする市民性、いわゆるシチズンシップを地域の活力の源とし、行政や市民、各種団体や企業など、多様な主体との協働により地域課題の解決や地域の持続的な発展に向けた取組を進めていくことなどを目的に、現在「西宮市参画と協働の推進に関する条例」の見直しに取り組んでおります。
令和5年7月に同条例評価委員会からいただいた提言書の内容に基づき、市民をはじめとする多様な主体同士の協働が円滑に進むよう市が環境づくりに取り組むことや、市民一人ひとりが地域において人とつながり支えあいながら地域が抱える課題を共有し、地域の持続的な発展に向けて自主的・主体的に活動していただきたいという趣旨を盛り込むことなどを検討しながら、令和7年度中の条例改正に向けて、引き続き取り組んでまいります。
また、多様な主体との協働による持続可能な地域社会を形成していくために、公民館・市民館・共同利用施設などの市民利用施設を再編し、地域課題の解決につながる様々な機能を備えたコミュニティ施設として、一元管理することを目指します。
まずは公民館が、地域と行政が共に地域課題を解決するための拠点となるよう、公民館機能の再構築や複合化に取り組みます。令和7年度は、地域における多様な主体が利用可能となるよう運用を改善するとともに、環境、防災、消費生活、地域共生などの市役所内各部署と連携した、地域課題解決型学習を推進します。
本市はこれまで、地域活動を支えるために様々な取組を行ってきました。その内容は多岐に渡り、それぞれ意義があるものの、市側の所管が分かれているなど、縦割りであるがゆえにその効果が限定的であった面も否定できず、より効果的、合理的な体制にしていかねばならないと考えています。また、自治会などの地域団体では、活動の担い手の高齢化や、住民のライフスタイルの多様化などに起因する多くの課題に直面しており、市の支援体制の充実が求められています。
市民交流センターと大学交流センターを再編した新たな施設では、これまで培ってきたNPO支援や学生・大学との連携のノウハウを生かして、地域団体や市民、学生、NPO、大学や企業といった多様な主体を有機的につなぐ役割を担い、地域課題の解決に向けた活動を支えていきます。
令和8年度の供用開始を予定している(仮称)越木岩センターにつきましては、併せて整備を行う図書館や地域交流スペースを有効に活用し、地域の拠点施設として、多世代にわたる市民の居場所となり、そこで行われる学びや交流が豊かな地域づくりにつながるよう、開館に向けた準備を進めてまいります。
西宮中央運動公園及び中央体育館・陸上競技場等再整備事業では、防災機能の強化を図るとともに、公園とスポーツ施設の一体的整備による相乗効果で、賑わいと新たなコミュニティを創出することを目指して整備を進めております。しかしながら、埋蔵文化財確認調査の結果、大規模な本発掘調査を行う必要があり、事業費及び工期が変更となる可能性が非常に高いため、各種調整を行っている状況です。影響をできるだけ軽減する方策について検討を重ねるなど、引き続き調整を図ってまいります。
本市の文化芸術振興の拠点であるアミティ・ベイコムホールを含む市民会館につきましては、竣工から57年が経過していることから、機能を適切に維持していくため、老朽化対策として大規模修繕を実施する予定としており、その準備段階として長寿命化に向けた設計及び工事時期における各種課題の整理を引き続き行ってまいります。
中小・小規模事業者支援としましては、西宮商工会議所を中心に国・県の支援機関などとも連携し、DXへの対応や人材不足の解消、より良い働き方の創造など、事業課題解決につながる取組を引き続き支援します。また、ワンストップで起業を支援する「にしのみや起業家支援センター」を通じて、安定した起業者数の増加を図ってまいります。
令和6年度に実施しました「女性デジタル人材育成プロジェクト」につきましては、「でじたる女子活躍推進コンソーシアム」との連携協定に基づき、人材育成や雇用につながるよう、引き続き支援してまいります。
5 環境・都市基盤、安全・安心
次に、基本計画の第5部「環境・都市基盤、安全・安心」についてです。
誰もが安全・安心で、快適な毎日を過ごすためには、生活インフラの整備・充実が不可欠です。ごみの減量・再資源化や、近年多発する集中豪雨による浸水被害への対策のほか、防災・消防・救急の体制強化などを進めてまいります。
環境学習においては、市民、事業者、行政など、多様なステークホルダーが共に考え、自発的に行動していくことが大切です。今ある環境を守り、次の世代につないでいくことを目指し、中学生に対する環境学習の機会提供の充実や、大学と連携した取組など、様々な手法で引き続き環境学習のバージョンアップに取り組んでまいります。
市制100周年を迎える本年、次の100年に向けて、本市の豊かな自然やそこで育まれた豊かな心、先人から引き継がれてきた文化・伝統・知恵などを未来に引き継いでいくために、環境学習拠点のあり方についても検討を進めます。本市に残る自然の浜辺は、住民の皆様によって守られたという歴史があり、本市の良好な環境を守る姿勢の原点となった象徴的な場所です。その甲子園浜に立地する自然環境センターを、環境学習の推進拠点として継続的に活用しつつ、環境に恵まれたまちを次の世代へとつなぐ新たな原点となるよう、施設の規模や手法などを検討し、骨組みをまとめてまいります。
本市では令和3年に表明した「2050ゼロカーボンシティにしのみや」を目指して、全庁的に環境問題への取組を進めているところです。公共施設のLED化、再生可能エネルギー設備や電動公用車の計画的導入のほか、リバースオークションを活用した低価格な環境価値付き電力の利用など、公共施設におけるCO2フリー電力の調達を第一としつつ、経費の縮減にも配慮してまいります。また、個人住宅等に対しましても、再生可能エネルギーや省エネルギー設備の普及促進を加速するため、引き続き国の交付金等を活用しながら取組を進めるとともに、西宮商工会議所や企業との連携により効果を波及させてまいります。
令和4年度に指定ごみ袋制度を導入して以降、生活系ごみの排出量は減少し、同時にごみの再資源化率は向上しており、着実にごみの減量・再資源化が進んでおります。更なる取組として、令和8年度からの新破砕選別施設の稼働開始に合わせ、生活系ごみの分別区分・収集回数の変更を決定しており、同時期に製品プラスチックの分別収集も開始することから、令和7年度には、冊子の配布や説明会の実施など、市民の皆様に対する周知啓発を進めてまいります。
斎園事業につきましては、多死社会の到来を踏まえた墓地の適切な供給を行うため、空き区画となった墓地については早期に公募できるよう整理を進めるとともに、計画に則り甲山墓園など市立一般墓地を公募します。なお、白水峡公園墓地については合葬式墓地の常時募集を継続するほか、一般墓地の常時募集の実施を目指します。また、多様な墓地ニーズに対応するため、合葬式墓地の申込状況を注視しつつ、墓じまいされる方に対する支援策を検討します。その他、火葬場設備維持などに係る財源確保を目的とし、残骨灰に含まれる有価物を収益化できるよう残骨灰処理の見直しを行います。
上下水道事業については、老朽化が進む施設の更新のほか、南海トラフ地震や局地的な豪雨などへの災害対策として、管路や処理場等の耐震化と治水安全度を向上させるための雨水浸水対策などに引き続き取り組んでまいります。一方で、人口減少に伴う料金収入の減少や、物価の上昇等による費用の増大により、経営状況はますます厳しくなることが見込まれております。これらの施策を着実に進めていくため、更なる経営改善に努めるとともに、料金・使用料の見直しについても検討してまいります。
道路につきましては、橋梁などの施設において長寿命化や耐震対策などの維持管理に努めるとともに、幹線道路等の整備を進めてまいります。北部地域においては、国道176号(名塩道路)の全線開通に向けて、引き続き国への働きかけを行ってまいります。また、沿線の開発事業にあわせて山口南幹線の道路整備を進めます。南部地域では、門戸仁川線などの道路整備や、小曽根線などの道路改良を着実に進めてまいります。
阪神・淡路大震災から30年が経過しましたが、この間、社会情勢など本市を取り巻く状況の変化に加え、東日本大震災や能登半島地震等の大規模災害から得た新たな知見や教訓、また残された課題など、市が取り組まなければならない防災・減災対策は多岐にわたっております。
特に大規模災害時に問題の多い物資供給について、国が速やかに被災自治体へ必要物資を緊急輸送する「プッシュ型支援」の制度が運用される中で、被災自治体の支援受入能力の不足が問題となっており、本市においても、国からの支援物資がスムーズに被災者へ届けられるよう、民間運輸事業者のノウハウを積極的に活用し災害時の物資受入れ及び供給体制を見直してまいります。また、災害時の情報通信手段の多重化の面から、昨今のスマートフォンの普及率向上や、より多くの市民へ緊急情報が伝達可能となる点などを踏まえ、プッシュ型で緊急情報を届ける防災アプリの開発に着手してまいります。
消防体制の強化といたしましては、市立中央病院と県立西宮病院の統合再編に合わせ、「(仮称)西宮総合医療センター」敷地内において、消防局と医療機関の連携拠点となる救急ワークステーションの建設工事に着手するとともに、救急隊員に対する教育体制を更に充実させ、救急救命処置等の質をより高め、迅速な出動が可能となるドクターカーを通じて、傷病者の救命率向上を図るための効果的な運用体制の構築に向けて取り組んでまいります。また、増加し続ける救急需要への対応といたしましては、救急業務を安定的かつ持続的に提供できるよう救急車を増車し、救急搬送体制を強化してまいります。
6 政策推進
次に、基本計画の第6部「政策推進」についてです。
現在本市では、財政基金取崩に依存しない財政体質の確立に向け、抜本的な財政構造改善に取り組んでおります。これまで、まずは市民生活に影響の少ない部分について重点的に取り組むべきとの考えに基づき、内部経費適正化によるコスト削減等の実施により、様々な見直しを実施してまいりました。また、人件費の抑制については、「定員管理計画」に基づき人員の抑制を図るとともに、給与水準について国や近隣他都市の水準を参考としつつ、本市独自の制度で均衡を失しているものは早期に適正化を図るべく、取組を進めております。
財政収支の均衡を図り、持続可能な市政運営を実現するためには、これらの取組と併せて、市民サービスに一定の影響が生じる取組も必要となってまいりますが、その影響が限定的なものや、内部経費等の見直しについては、「西宮市財政構造改善実施計画」にお示しした項目に留まることなく、積極的に進めてまいります。あわせて、市有地の売却等によって一時的な歳入増に取り組むとともに、施設使用料の適正化、ふるさと納税や公共施設へのネーミングライツ導入の取組強化など、経常的な歳入を増やすための取組も進めることで、早期の財政構造改善を図ってまいります。
また、計画において効果額が未定となっている項目については、内容の具体化を早急に進めるとともに、新規・拡充事業に見合った事業のスクラップや、目標とする財政指標を設けるなどして、中長期的にバランスを保った財政運用を進められるよう取り組んでまいります。
これまで寄附収入額を流出額が大きく上回る状況が続いているふるさと納税につきましては、令和6年度から若手職員による検討を踏まえた強化の取組を開始し、若干の増額が見込まれているところですが、令和7年度からは、ふるさと納税関係業務全般を支援する中間事業者を導入し、新規返礼品の開拓、登録ポータルサイト数の増加、返礼品写真の改善などの強化に取り組み、寄附収入の増額を目指してまいります。また、企業版ふるさと納税についても、自治体と企業のマッチングサービスの利用や、広報活動の充実などにより、寄附収入の増額を図ってまいります。
公共施設マネジメントについては、令和6年度から、公共施設の整備等に当たり、施設総量の縮減目標との整合性を、事前協議において確認する仕組みを導入いたしました。令和7年度においても、行政経営改革本部の専門部会である公共施設マネジメント推進部会において、施設整備における事前協議を行うなど、引き続き施設総量の縮減に向けた取組を進めてまいります。
財政構造改善を図るためには、DXを積極的に推進し、大胆な変革を行うことも重要です。これまでの取組としましては、令和5年度に策定した「西宮市ペーパーレス化行動計画」や「電子的処理による事務効率化等に向けた指針」を踏まえ、令和3年度と比較して、紙の使用量を2割減少させるとともに、電子申請可能な手続数を13倍増加させたところです。
令和7年度以降も、手続や面談のオンライン化、書かない窓口などの「窓口DX」の一層の推進、公金収納におけるeLTAX(エルタックス)の活用、電子請求システムの導入などの取組に加え、デュアルディスプレイの導入、物品調達事務の効率化、印刷機器の集約化に向けた検討、内部事務関連システムの導入や更新のほか、ローコードツールやAIなどの活用促進、DX人材の育成などの取組を進め、市民の利便性向上と内部事務の効率化とを両立させた、大胆な変革を実現してまいります。
これに加えまして、中堅・若手職員による庁内横断型組織として「庁内改革イニシアティブチーム」を立ち上げ、DXの推進、組織の活性化や組織風土の改善など、持続可能な市役所体制の実現に向けて取り組んでまいります。
近年、インターネットやSNSの普及など情報発信を取り巻く環境が大きく変化していることから、市においても、広報媒体の特性を生かした広報を実施する必要があり、そのための指針となる「西宮市広報戦略」を令和6年9月に策定しました。令和7年度はこの戦略に基づき、「伝える」広報から「伝わる」広報へと進化するよう取組を進め、市からの「広報」と市民や地域の声を聴く「広聴」から生まれるコミュニケーションについて一層の充実を図ることにより、地域課題の共有やシチズンシップの醸成、ひいては「参画と協働」のまちづくりの推進へとつながっていくことを目指してまいります。
冒頭でも申しましたが、今年は市制施行100周年を迎えることを記念し、アミティ・ベイコムホール及び周辺で記念式典や関連イベントを実施いたします。あわせて、本市100年のあゆみをまとめた記念誌を作成し、WEBで展開してまいります。また、ふるさと納税型クラウドファンディングを取り入れた「まちなかにぎわい事業推進補助金」を創設し、市民や事業者、団体等の皆様に実施していただく100周年記念事業を支援することにより、オール西宮の体制で100周年を祝う機運を醸成し、賑わいの創出を図ってまいります。
様々な事業の実施を通じて、本市の歴史や未来への展望を広く市民の皆様と共有し「文教住宅都市・西宮」を次世代へ引き継いでまいります。
予算
次に、令和7年度予算について概要を説明いたします。
厳しい財政状況の中、財政構造改善の取組を着実に進めつつ、歳出では、子育て支援などの社会保障関係経費や清掃施設・学校施設などの公共施設の老朽化対策、まちづくりへの投資に資する事業などを重視した予算編成を行いました。
歳入では、根幹となる市税収入については、定額減税の大幅な縮小や給与所得の伸びなどにより増収となる見込みです。市有地の売り払いや市債の活用も積極的に進めておりますが、喫緊の行政課題への対応に必要となる財源を確保するため、不足する額については、財政基金等から繰り入れることとしました。
このように編成いたしました新年度予算は、
一般会計 2,226億 6,323万円 前年度比9.6%増
特別会計 970億 5,078万 2千円 前年度比2.8%増
企業会計 465億 5,046万 9千円 前年度比0.4%増
合 計 3,662億 6,448万 1千円 前年度比6.5%増
となっております。
以上、新年度の市政に臨む私の決意と施策の大要を申し上げました。
議員各位並びに市民の皆様のご支援をお願い申し上げますとともに、予算案をはじめとする諸議案にご賛同賜りますようお願いいたします。
ダウンロード(PDF版)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()